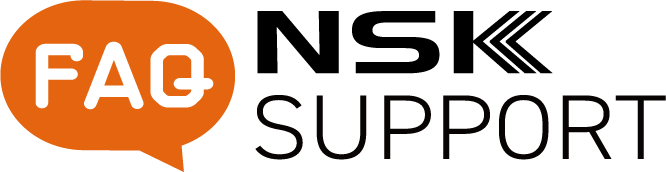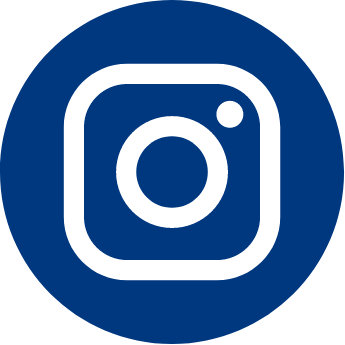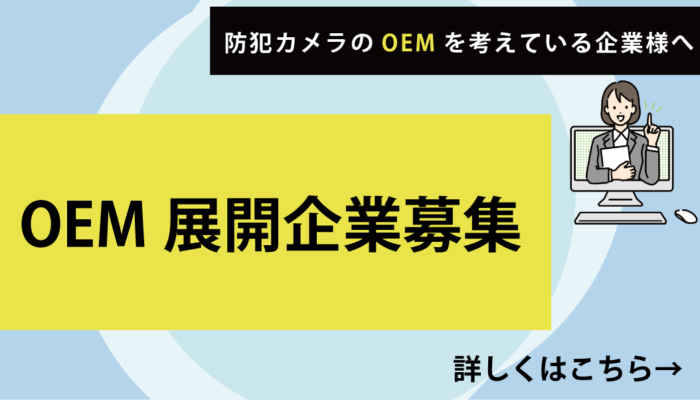漁港では、屋外用防犯カメラは潮風の塩害によりカメラの劣化が早く、また従来の映像録画機能のみの古い機種では、録画映像が不鮮明で証拠不十分となり“使えない映像”になっているケースも少なくありません。
そこで、漁港における過酷な環境下に適し、万が一の事態に備えるためには、最新のAIカメラへの買い替えが有効な選択肢といえます。
今回は、漁港に最適な屋外用防犯カメラの選び方と注意点について解説しますので、最後までご覧になり、参考にしてください。
目次
なぜ今、防犯カメラの買い替えが必要なのか?

現在多くの漁港で防犯カメラが設置されていますが、古い機種では万が一に犯罪やトラブルが起こってしまった場合、録画映像が不鮮明で映像として役に立たないケースも増えています。
なぜ今買い替えが求められているのか、その背景と理由について紹介していきます。
漁港で使われるカメラの劣化と故障リスク
漁港という環境は、塩分を含んだ潮風、紫外線、飛砂、強風、暴風雨、そして海鳥の糞害など、精密機器にとっては“過酷の極み”ともいえる状況が常に続いています。
特に十年程も設置されているカメラでは、こうした環境に耐えてきたとしてもいつ動作に支障が出てしまうかわかりません。
たとえば、レンズの曇りや画面のノイズによる画質の劣化・赤外線照射距離の低下・録画機能の不安定化などにより、いざトラブルが起きた際に役に立たず、「起きてはならない事故を見逃してしまう」という要因になってしまいます。
ある港では魚市場の裏手に設置していたカメラが塩害でレンズが完全に白濁してしまい、肝心の盗難事件発生時に映像がまったく残っていなかったという事例もあるため、このような“設置しているのに意味がない”状態では非常に危険な環境となってしまいます。
最新AIカメラが持つ防犯力と監視精度の進化
最新の防犯カメラは、従来の単なる記録装置から「監視支援システム」へと進化しています。
特にAI搭載モデルは、映像に映った人物の動きや行動パターンから異常を検知し、管理者へ即座に通知する機能が備わっています。
この機能により、管理者は「何かあったあとに録画映像を見返す」のではなく、「何かが起きそうな段階で通知を受け、現場対応に動ける」という体制を整えられます。
たとえば、深夜2時に通常では誰も近づかない場所で人影を検出した場合、スマートフォンに通知が届き、すぐに遠隔でリアルタイムの状況を確認し、適切な対処が可能となります。
また、録画映像はクラウド上に保存されものもあり、カメラ自体が破壊されても証拠は消えないため、“万が一”の場面での対応力を劇的に高めてくれる存在です。
補助金や自治体支援で導入ハードルが下がっている現状
防犯カメラの買い替えを検討しても「予算がない」と躊躇してしまう現場は多いです。
しかし現在では、政府や自治体が実施している補助金・助成金制度を活用できるケースがあります。
ただし、補助金制度の内容や実施時期は自治体によって異なるので、まずはホームページで確認後、相談窓口へお問合わせすることがおすすめです。
また、漁港(漁業)は日本及び市区町村の重要な産業でもあるため、管理組合が自治体に現在の状況やこれからの対策などを訴えることで、自治体負担で防犯カメラを設置してくれることも考えられます。
そのため、まずは対象となる自治体の防犯安全課や農林水産課へ相談しましょう。
「もう少し様子を見てから」「壊れてからでいい」という判断では、結果的に高くつくため支援制度が整っている今こそ、更新・買い替えに踏み切るタイミングです。
漁港においてAIカメラに買い替えるときのおすすめな選び方!

防犯カメラの買い替えを検討する際には、漁港という環境に合った性能を把握することが不可欠です。
ここでは、カメラの導入前に知っておきたい基礎的なスペックについて解説します。
防塩・防水・耐久性の重要性
漁港に設置する防犯カメラは、潮風や飛沫、塩分を含む湿気に常時さらされる過酷な環境に置かれます。
常に潮風が吹き、塩分が金属や樹脂に浸透すると外装の腐食や内部のショートが発生しやすくなるため、最低でもIP66以上の防水・防塵性能に加え、ステンレスや耐塩害アルミ素材を採用したハウジングが必須です。
そして、ケースだけでなくケーブルやコネクタ部分の防錆・防湿対策も施されていないと、数年以内に故障する恐れもあります。
また、強風による転倒や飛来物による破損を防ぐため、本体の耐久性だけでなく、取り付け部の強度にも注意が必要です。
実際に、台風直後にカメラが支柱ごと倒れてしまい録画も通信も不通になったという事例もああるため、カメラ本体から配線・設置まで、総合的な耐久性と耐候性を考慮することが必要です。
「防犯用」ではなく「港湾・沿岸向け」と明記されたモデルを選ぶことが安定した長期的な運用を実現可能にします。
夜間撮影・赤外線機能は必須
漁港のトラブルは多くが夜間や早朝の薄暗い時間帯に発生するといわれています。
しかし、漁港では「夜になると映像がほとんど見えない」というカメラが使われているケースも少なくありません。
そのため、カメラには暗所でも明瞭に映像を記録できる赤外線LED機能やスターナイトビジョン(超高感度暗視)機能が求められます。
赤外線照射機能を持つモデルであれば、光のない環境でも人物の輪郭や動きがはっきりと記録できます。
また、最近では暗所でもカラーで撮影できるモデルもあるため、不審者の顔と服装が鮮明に記録され、警察への証拠提供により犯人逮捕に繋がりやすくなります。
特に、照明が届かない桟橋や倉庫周辺では、赤外線照射距離が20~30m以上ある機種を選ぶと安心です。
AIの検知機能による早期察知
従来の録画機能のみの防犯カメラでは、不審者の侵入や密漁者の動きに対して、事件が発覚してから気づくため、手遅れになるケースがほとんどです。
そのため、AI機能を備えたカメラであれば、人や車の動きを自動で識別し、特定エリアへの侵入や不審な滞在行動などをリアルタイムに検知・通知することができます。
また、通知や映像録画だけでなく、録音データや警告音を発することも可能であるため、巡回の省人化と同時に、トラブルを未然に防ぐ“抑止効果”にも期待できます。
AI搭載による防犯カメラでは、従来の“記録するだけ”のカメラから、“判断して知らせて犯罪を起こさせない”カメラへの体制を整えることが推奨されています。
遠隔監視対応と録画タイプを運用に合わせて選ぶ
遠隔監視の通信方式
AIカメラの性能を最大限に活かすには、遠隔監視ができる環境を整えることが大切です。
特に漁港では「常に誰かがカメラを見ている」体制が難しいことも多く、スマートフォンやPCからの映像確認ができるかどうかは極めて重要なポイントとなります。
通信方式には以下の2つがあります。
- LTEモデル:SIMカードを用いて携帯通信回線を利用。インターネット回線がない場所にも対応可能で、遠隔地でも設置しやすい。
- Wi-Fiモデル:既存の無線LAN環境を利用。通信コストを抑えたい場合に適しているが、回線の安定性に注意が必要。
たとえば、無人の荷揚げ場にLTEタイプのカメラを設置した例では、漁協の担当者が出張先からでも映像を確認でき“もしもの時も見逃さない”運用が可能となります。
録画や保存方法
漁港の監視用途では、主に「SDカード録画」「NVR(ネットワークビデオレコーダー)」「クラウド保存」の3方式から選びます。
録画方法(SDカード/NVR/クラウド)も
- SDカード録画:カメラ本体に直接録画できる最もシンプルな方式。電源があれば即運用可能で、コストも安価。保存容量が小さく、録画期間は数日〜1週間程度が限界。
- NVR(ネットワークビデオレコーダー)録画:複数のカメラ映像をLANで接続し、1台の録画機器で一元管理できる方式。保存容量が大きく、最大数ヶ月の記録が可能。ただし設置や配線に専門的な知識が必要で、初期費用はやや高め。
- クラウド録画:インターネット経由で録画データを外部サーバーに保存する方式。カメラが破損・盗難されても映像は守られ、スマホやPCで即時確認・共有が可能。月額利用料が必要で、通信環境の安定性が前提条件。
カメラの設置台数や設置場所に適した録画方法を選択することが大切です。
漁港におけるカメラ設置の注意点とトラブル防止策
カメラの選定と同様に、設置時の工夫や注意点も防犯効果に直結します。
通信・電源インフラの現地調査は必須
漁港は人が行き交う街とは違い、通信回線のインフラ整備状況がまちまちです。
設置予定場所が無線LANの通信環境が整っていない場合は、LTE通信を検討する必要もあります。
万が一、通信が不安定なエリアの場合、録画がクラウドに保存されない、通知が遅れるなど運用に支障が出るリスクもあるため、ネットワーク安定性とバックアップ対策を含めた設計が重要です。
また、電源確保ができる状況なのか確認する必要もあります。
設置したい場所があったとしても外部電源の有無によって選ぶモデルも変わってきます。
もし外部電源が確保できない場合は、ソーラーパネル搭載タイプもしくはバッテリータイプなどを検討する必要があります。
そのため、設置を検討している場所の環境を把握して適切なカメラを設置するためには、プロによる現地調査が重要です。
設置場所・台数・メンテナンスなどの事前計画
AIが搭載された防犯カメラの導入は、製品選びだけでなく、「どこに・何台・どう管理するか」まで計画することが、防犯効果と運用効率を大きく左右します。
漁港のように広く死角の多い現場では、主要な出入口・資材置き場・係留場所など、カメラを設置すべき場所の優先順位を事前に整理しなければ、死角が残り、トラブルの見逃しにつながるリスクがあります。
また、台数は多ければ良いわけではなく、敷地の構造や視野角に応じて最適なカバー率を計算する必要もあります。
そして、潮風や天候の影響を受けやすい屋外では、定期点検・レンズ清掃・録画状況の確認といった運用保守の体制づくりも重要です。
導入後に「設置が甘かった」「誰もメンテナンスしていなかった」とならないよう、設置場所・台数・管理ルールを導入前から具体的に計画しておくことで、長期的な効果と安心が確保できます。
まとめ
漁港では、さまざまな犯罪やトラブルが発生し、古いカメラでは万が一の際に証拠が残らず、異常に気づけないという深刻な問題が浮き彫りになっています。
特に漁港のような過酷な環境では、機器の劣化スピードが早く「動いているつもり」が命取りになりかねません。
防塩・防水・夜間対応・AI検知・遠隔監視といった最新機能を備えたカメラであれば、こうしたリスクを事前に察知し、迅速な対応につなげる体制を整えられます。
「カメラがあったのに、意味がなかった」と悔やまないためにも、設備の見直しと買い替えを前向きに検討しましょう。
もし、屋外用の防犯カメラやAI搭載防犯カメラの選び方について不安に感じている方、詳しい情報が知りたいという方は、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
弊社専門スタッフがお悩みやお困りごとをヒアリングさせていただき、お客様のニーズに合った最適なご提案をさせていただきます。
NSKと一緒に、セキュリティレベルの高い防犯対策や効率的な運用のシステム構築をしていきましょう。
株式会社NSKは監視カメラ・防犯カメラ・セキュリティ機器のメーカーです。
製品に関する詳細な情報が知りたい方、導入に対して不安に思っている方、お困りごとなどがありましたら下記の「お問い合わせ」よりお気軽にご相談ください。
専門スタッフがわかりやすく丁寧にご説明させていただきます。